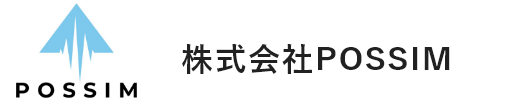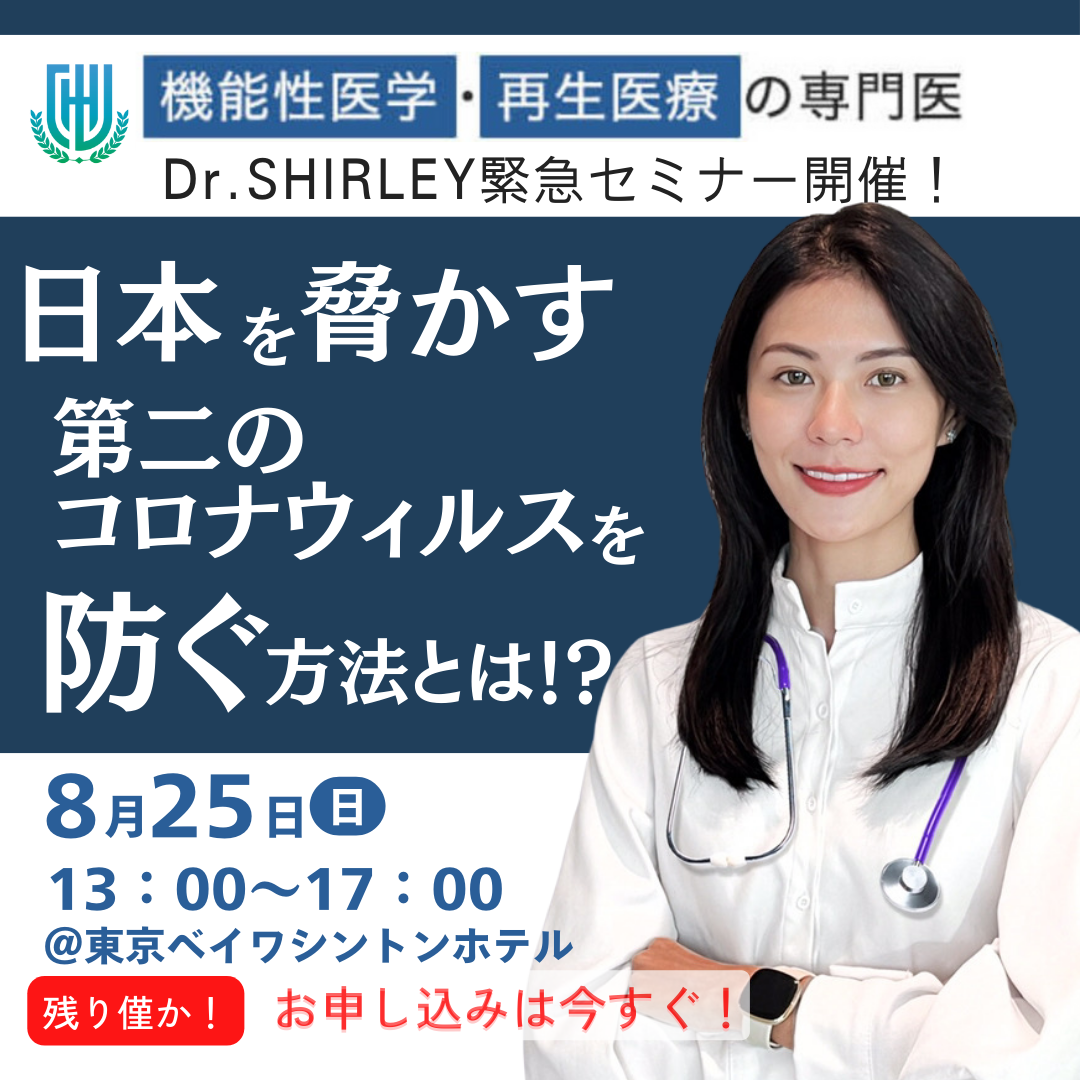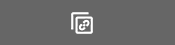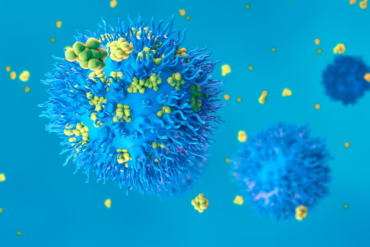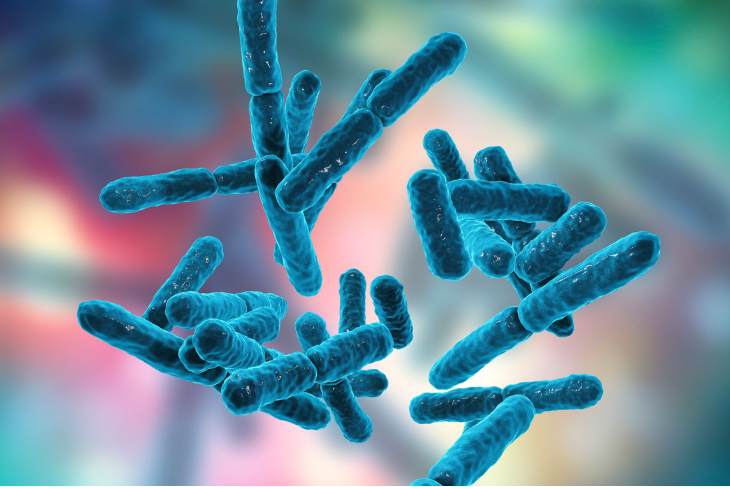
ビフィズス菌を多く含む食品や、ビフィズス菌の働きについてご存知ですか?ビフィズス菌を摂取することで、私たちの腸内を健やかに保つことができ身体全体の健康維持も叶います。
ビフィズス菌を多く含む食品を一覧でご紹介し、1日の推奨摂取量などもお伝えいたします。腸内環境を整えて心と体を健全に保ちたい方は、ぜひ読んでください。
ビフィズス菌の基本
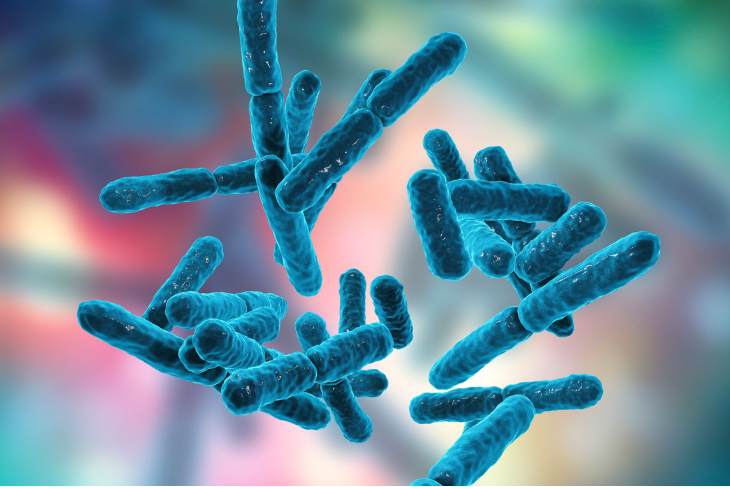
まず、ビフィズス菌の基本について理解を深めていきましょう。
ビフィズス菌とは?
「ビフィズス菌」は1899年、フランス・パスツール研究所のHenry Tissier博士により、赤ちゃんのお腹(便中)から発見されたのが始まりです。
この発見により、ビフィズス菌の中にはアルファベットのY字のような特徴的な形をしたものがあることがわかり、そこからラテン語で「分岐」を意味する「ビフィズス」という名前が付けられました。そもそもビフィズス菌はお腹に良い働きをする菌として広く認知されており、善玉菌の代表格ともいえる菌です。
そんなビフィズス菌には実は整腸作用の働きのみならず、アレルギー症状の緩和・認知機能の維持など、身体全体の健康に良い影響を与える菌であることが最近の研究により明らかになってきました。
またビフィズス菌と並んでよく知られている菌に「乳酸菌」があり、両者とも同じ善玉菌の仲間ですが、実は全く別の菌です。
ビフィズス菌と乳酸菌の違い
ビフィズス菌がヒトや動物の大腸に住んでいる菌なのに対し、乳酸菌は自然界に広く住んでいます。ビフィズス菌は酸性に弱く食物繊維を好む性質を持っているため、酸素がほとんど存在しないばかりかヒトが消化できない食物繊維が多く存在する大腸に適応している菌です。
一方、乳酸菌は食物繊維が苦手なため、小腸下部を好んで住みついている菌です。働きとしては両者とも、腸内を酸性にして悪玉菌の繁殖を抑制し、腸の調子を整える整腸作用があります。
ビフィズス菌のはたらき
ビフィズス菌は大腸に一番多く存在し、腸内で有害な菌である悪玉菌の増殖を抑制する働きをしています。その働きにより免疫力が高まり、食中毒菌・病原菌などに負けない体づくりが行えたり、体内での腐敗産物の生成を抑制する腸内環境づくりを行ったりしています。
またビフィズス菌は、葉酸やビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12等のビタミンB群や、血液の凝固にかかわるビタミンKを合成する働きがあるとともに、短鎖脂肪酸(酢酸)という機能性成分を作り出す働きがあります。
短鎖脂肪酸には以下の働きがあり、大腸で短鎖脂肪酸が多く作られることが、健康維持のカギと考えられています。
〈短鎖脂肪酸の働き〉
・悪玉菌の働き及び増殖の抑制
・大腸の働きを活発にして便通を改善する
・腸管バリア機能を高め、病原菌が体内に侵入しないようにする
・免疫反応の制御
・血糖値のコントロール
・脂肪の蓄積を抑制し、太りにくい体質にする
ビフィズス菌を多く含む食品一覧

ビフィズス菌を多く含む食品を、表にまとめてご紹介いたします。
ビフィズス菌を多く含む食品一覧
| 食品名 | 効果 | 相乗効果(育菌効果)を狙える組み合わせ | 特徴 |
| ヨーグルト | 乳酸菌が含まれており、直接善玉菌を摂取できる食品。商品によってはビフィズス菌入りもある。 | はちみつ・リンゴ・バナナなどのオリゴ糖を多く含む果物類と一緒に食べると良い。 |
〈発酵食品〉 |
| ぬか漬け | 他の発酵食品に比べ、含まれている菌の数は少ないが、菌の種類が非常に豊富。摂取することで一度に乳酸菌・酪酸菌・酵母菌などの12種類から30種類もの善玉菌を摂取できる。 | セロリ・キクイモ・アボカド・きゅうり・キャベツなどがおすすめ。 | |
| 甘酒 | 酒粕・米麹から作られ、麹菌・酵母菌が含まれている。 | 酒粕から作られる甘酒には少しアルコールが含まれているため、アルコールを避けたい人には不向きのため、米麹で作られた甘酒を選ぶと安心。 | |
| 漬物 | 植物性乳酸菌が含まれており、強い腸内作用が期待できる。なんと30を超える乳酸菌が含まれており、様々な良い効果をもたらしてくれる。 | 食物繊維を多く含む食材を使って漬物を作ると良い。例えば、キャベツ・大根・きゅうりなど。 | |
| 納豆・味噌・醤油 | 麹菌・乳酸菌が豊富に含まれているが、塩分も多く含まれているため、過剰に摂取しないように注意する必要がある。 | オリゴ糖や食物繊維を多く含む野菜類・海藻類との相性が抜群。玉ねぎ・キャベツを加えたり、わかめ・もずく・ひじきなどと和えると良い。 | |
| 大豆・豆腐・おから | 肌のハリ・弾力を与える成分を多く含み、良質な大豆をビフィズス菌で発酵させることで、大豆に含まれるイソフラボンを活性化させられる。 | 食物繊維を多く含む野菜などと組み合わせることで、相乗効果が狙える。 | |
| バナナ | 難消化性のオリゴ糖(楽とオリゴ糖)・食物繊維が多く含まれ、即効性のエネルギーとして使える糖質も豊富に含まれている。ラクトオリゴ糖は、腸内のビフィズス菌を増やし、お腹の調子を整える。 | 乳酸菌・ビフィズス菌を含むヨーグルトと組み合わせると効果的。 |
〈オリゴ糖・食物繊維〉 |
| きのこ類 | 腸内環境を整えたり、免疫力を高めたりする効果がある。また精神面を安定させ、肥満抑制効果もある。 | オイル・醤油・こしょう・ショウガなどと合わせて食べるのはおすすめ。ところが、唐辛子・ピーマン・トマト・レモンとの組み合わせは避けるべき。 | |
| ゴボウ | 水溶性・不溶性食物繊維・オリゴ糖を多く含んでいる。 | 納豆・人参などの他の野菜類などと組み合わせることでより善玉菌を増やせる。 | |
| 海藻類 | ゴボウと同様、水溶性・不溶性食物繊維を含んでいる。 | 味噌汁・鍋・煮物・和え物など、様々な料理に活用できる。 |
選び方・食べ方ポイント
ビフィズス菌が多く含まれている食品を選ぶ際におすすめの選び方は、ビフィズス菌を生きて腸まで届けられるかが最大のポイントです。例えばヨーグルトはビフィズス菌を多く含む食品として良く知られていますが、朝の一番お腹がすいている時間に食べるのは逆効果です。
なぜならビフィズス菌は胃酸に弱く、まずは空っぽの胃に食べ物を入れ胃酸を薄くしてから、食後のデザートとして食べるのがベストな食べ方です。
また上記の表でも記載しましたが、ビフィズス菌を含む食品と何を一緒に食べるかで効果を増大させられます。特に意識せず食べたいと思われる方は、「和食」がおすすめです。
1日の摂取量は?
ビフィズス菌の1日の摂取量の目安は1日あたり20億個以上で、ヨーグルトだと1日200㎖を目安に摂取するのがベストとされています。またビフィズス菌は薬ではないため、一度に大量に摂取するより、毎日継続的に摂取することが大切です。
ビフィズス菌をサプリメントなどの耐酸性のカプセルで摂取する場合は、出来る限り速やかに胃を通過できるように空腹時の摂取が勧められていますが、一般的な食品で摂取する場合は食後に食べるようにすると胃酸の影響が少なると考えられています。
ビフィズス菌の健康効果

最後に、ビフィズス菌の健康効果について解説いたします。
腸内フローラのバランスが整う
ビフィズス菌の住処である大腸には、およそ1,000種類、100兆個もの腸内細菌が棲んでおり、これらを顕微鏡で見るとまるでお花畑のように見えることから「腸内フローラ」と呼ばれています。
ビフィズス菌を増やすことで、善玉菌・悪玉菌・日和見菌という3つの腸内フローラ(腸内細菌)のバランスが整います。日和見菌は悪玉菌もしくは善玉菌のどちらか多いほうの味方に付く性質を持っているため、悪玉菌よりも善玉菌が多い状態を保つことが、腸内フローラのバランスを保つポイントになります。
健やかな体作りが叶う
ビフィズス菌は私たちの食生活を豊かにするだけでなく、お腹の同居人として健康を日々サポートしてくれています。赤ちゃんの頃には腸内にいっぱい存在していたビフィズス菌も、加齢や生活の悪習慣・ストレスなどによって悪玉菌が増えていきます。
悪玉菌を増やさないためにも、日々ビフィズス菌を補給し腸内環境を保つ努力が大切です。
まとめ
ビフィズス菌は大腸に存在しますが、常に大腸に存在し続けられるわけではないため、毎日補充する必要があります。またビフィズス菌を増やすためには、ビフィズス菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を積極的に食生活に取り入れることが大切です。腸内フローラを育てる菌を摂取して、心も体も健康的な生活を送ってくださいね。