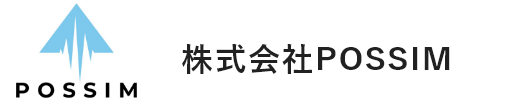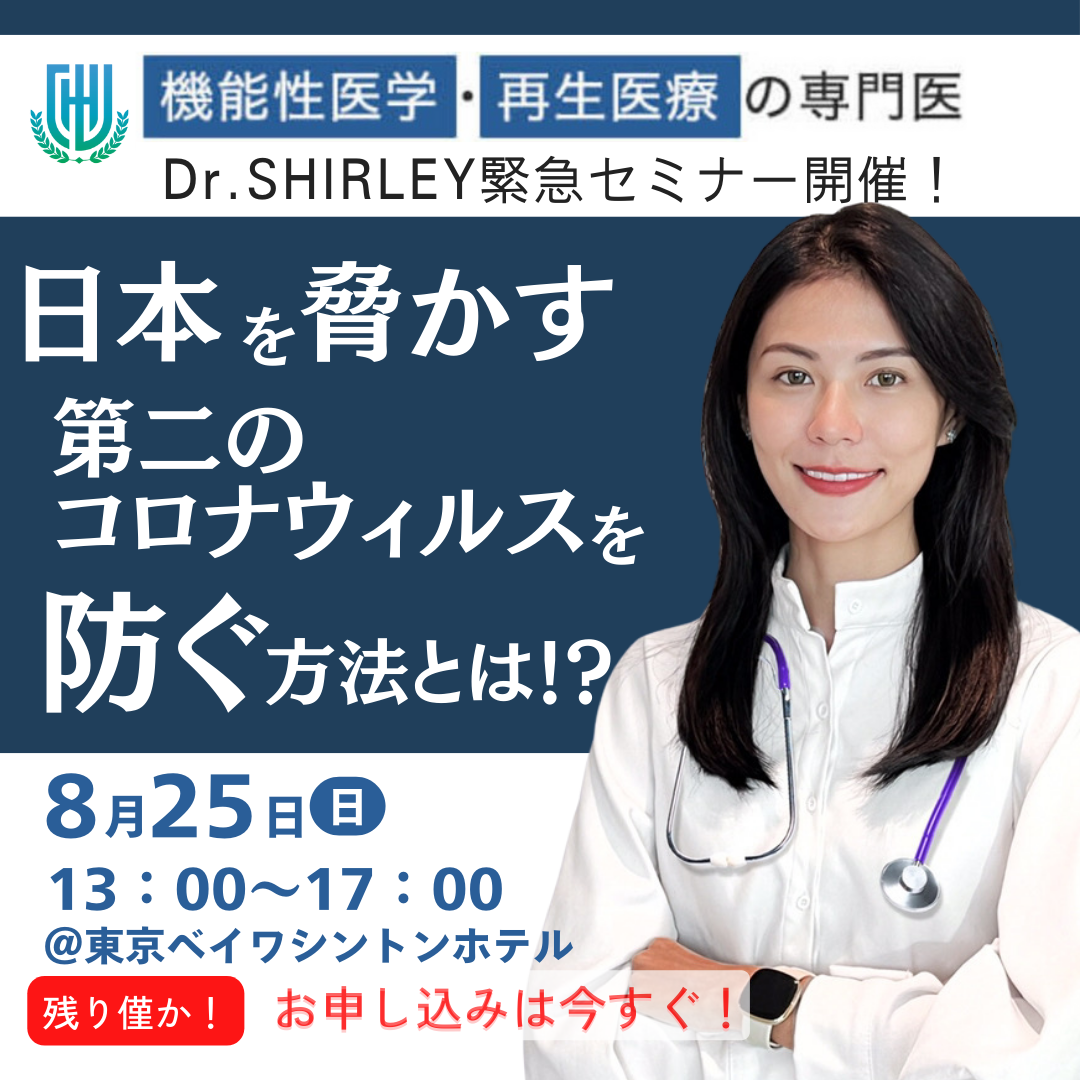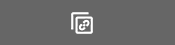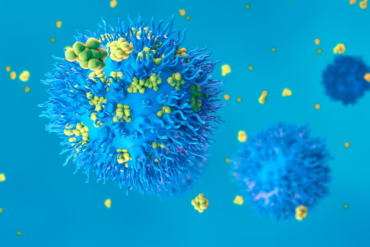緑茶には、私達の体に色々な効果効能があることが分かっています。この記事では、緑茶に含まれる栄養素や、緑茶を摂ることによる効果効能について解説していきます。
緑茶のきほん

まずは、緑茶の定義について説明していきます。
緑茶とは
緑茶とは、茶葉を発酵させずに作られたお茶の総称です。反対に、発酵させて作られたお茶には半発酵茶の烏龍茶や発酵茶の紅茶などがあります。
緑茶の種類
緑茶には、大きく分けて日光を浴びて出来た茶葉と、一定期間日光を遮断して栽培(被覆栽培)されたものがあります。被覆栽培で作られた茶葉は、日光に当たることにより強くなる苦味が抑えられます。そのため、旨みや甘味が強く、日光を浴びて光合成をした茶葉は、苦味が強いものが多い特徴があります。
・日光を浴びて作られた緑茶
煎茶、深むし煎茶、番茶 など
・被覆栽培の緑茶
玉露、かぶせ茶、抹茶 など
煎茶
緑茶の中で最も馴染みのある代表的なお茶。日光を浴びて栽培された茶樹から摘み取られた新芽を蒸して揉みながら乾燥させて作られた茶葉のお茶のことを言います。
深むし煎茶
煎茶の2〜3倍長く蒸して作られた茶葉のお茶のことを言います。甘みがでて渋みが少なく、濃厚な味わいが特徴です。
番茶
1、2番茶が摘み取られた後に出た遅れ芽が硬くなったものや、秋に摘んだ茶葉から作られたお茶のことを言います。地方によっても異なります。また、番茶は再加工されることもあり、その中にほうじ茶や玄米茶などがあります。
抹茶
20日以上日光を遮断して育てられた茶葉を蒸したあと、揉まずに乾燥させて石臼で引いた粉末のお茶。
玉露
20日以上日光を遮断して育てられた茶葉を蒸して、揉みながら乾燥させて作られた茶葉のお茶のことを言います。
かぶせ茶
玉露と煎茶の中間で、数日間日光を遮断して育てられた茶葉を蒸したあと、揉みながら乾燥させた茶葉のお茶のことを言います。
緑茶に含まれる栄養素

緑茶に含まれる栄養素について解説していきます。緑茶の中でも被覆栽培で作られたものは、テアニンやカフェインが多く含まれ、日光を浴びて作られたものはカテキンが多くカフェインが少ないという特徴があります。
ビタミン
緑茶にはいくつかのビタミンが含まれていますが、最も多いのはビタミンCです。ビタミンCは、水溶性ビタミンであり健康維持に欠かせないビタミンです。
コラーゲン、カルニチン、ホルモン、アミノ酸の合成に必要な栄養素です。その他、免疫機能や鉄の吸収促進などにも関係しています。また、強い抗酸化作用があります。
ミネラル
緑茶には、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウムなどのミネラルが含まれています。これらのミネラルは陽イオンといい、血圧の調整、神経や筋の活動、骨や歯の機能、細部膜の安定など、体内で色々な働きをしています。
ポリフェノール
ポリフェノールとは、強い抗酸化作用を持つ成分です。緑茶にはポリフェノールの一種である「カテキン」という成分が多く含まれています。カテキンは緑茶の苦味や渋み成分です。
健康効果としては、抗菌作用や抗ウイルス作用などがあるため、風邪や虫歯の予防効果があります。また、抗酸化作用があるため、老化や病気の予防や、動脈硬化や血糖値の上昇を抑える働きもあります。カテキンには色々な種類があり、特徴が少しずつ異なります。
カフェイン
緑茶にはコーヒーにも多く含まれるアルカロイドの一種であるカフェインが含まれています。特に被覆栽培で作られた鮮やかな緑色の緑茶にはカフェインが多く含まれています。
カフェインには、覚醒作用や血管拡張作用、利尿作用、脂肪燃焼作用などがあります。一方で、摂りすぎることにより健康被害を引き起こす可能性が高くなるということも分かっています。
テアニン
テアニンとは、お茶の旨みや甘み成分であるアミノ酸の一種です。被覆栽培で作られた茶葉に多く含まれ、玉露や抹茶などに多く含まれる成分です。
テアニンは、神経伝達物質であるドーパミンやセロトニンの濃度を変化させる働きを持ち、心身をリラックスさせる効果を持っています。研究でも、テアニンにはリラックス効果や集中力の向上、睡眠の質の改善の効果があることが分かっています。
緑茶の持つ効果効能

緑茶にはたくさんの栄養素が含まれているため、様々な健康効果があります。そのため、得たい効果に合わせて緑茶を選ぶのがおすすめです。
生活習慣病を予防する
緑茶に含まれるカテキンには、血中コレステロールの吸収を抑える効果や血糖値・血圧の上昇を抑える効果があります。また、ビタミンやカテキンには抗酸化作用があるため、生活習慣病の原因となる活性酸素を除去する働きがあります。これらの働きにより、緑茶には高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防効果があると言われています。
研究結果によると、緑茶をたくさん飲む人ほど循環器疾患、脳卒中、脳梗塞、脳出血の発症リスクが低減することが分かっています。特に、日あたり4杯以上飲む人においては、リスクの低減が顕著に現れています。また、女性においては、緑茶を頻繁に飲む人の方が胃がんの罹患リスクが低いというデータも。
老化を予防する
老化の原因には、酸化や糖化が関係していると考えられています。緑茶に含まれるカテキンには血糖値の上昇を抑える抗糖化作用や、酸化を抑える抗酸化作用があります。そのため、老化を予防する働きがあると言えます。
カテキンは、日光を浴びて作られた茶葉からできる煎茶、二番茶、三番茶などに多く含まれています。
風邪を引きにくくなる
緑茶に含まれるカテキンには、抗菌作用や抗ウイルス作用があります。また、緑茶に含まれるビタミンは免疫を高める働きがあります。そのため、緑茶には風邪の予防効果があります。また、緑茶を用いたうがいにおいてもインフルエンザや上気道感染症などの予防効果がある可能性が示唆されています。
脳が覚醒する
緑茶に含まれるカフェインには中枢神経興奮作用があります。そのため、摂取することにより眠気を解消したり、集中力が向上する効果があります。特にカフェインは、摂取後30分〜2時間程度で血液中の濃度が最大になります。そのため、上手に取り入れることで、勉強や仕事に集中することができ、生産性が上がるというメリットがあります。
反対に、摂取のタイミングや摂取量によっては、睡眠の質を低下させてしまう可能性もあるため、寝る4時間前までにするのが良いでしょう。
緑茶の効果的な飲み方

緑茶を効果的に飲むためには、タイミングや淹れ方も大切です。ここでは、効果的な飲み方について解説していきます。
緑茶を摂るタイミング
緑茶は、摂るタイミングにより得られる効果が異なります。食前や食事中に摂ることで、血糖値の急激な上昇を防ぎ、脂肪の吸収を緩やかにすることができます。しかし一方で、鉄分の吸収を妨げてしまうというメリットがあります。貧血傾向の方は、食事の前後1時間程度は空けるのが良いでしょう。
運動前に摂ると、脂肪燃焼効果を得ることができます。ダイエットの目的で摂りたい方にはおすすめです。また、寝る前に摂ると、カフェインの持つ覚醒作用により寝付きが悪くなったり、睡眠の質が低下してしまう可能性があります。そのため、睡眠の4時間前くらいから控えるのがベターです。
緑茶の美味しい淹れ方
実は緑茶は淹れ方により、栄養成分の溶出の仕方が異なります。緑茶に含まれる旨みとなるテアニンなどのアミノ酸類はお湯の温度に関係なく溶出しますが、栄養素であるタンニンやカフェインはお湯の温度が高くなるほど溶出しやすい傾向があります。タンニンやカフェインは溶出が多すぎると苦味や渋みが強くなるため、高温になり過ぎないのが良いでしょう。
・カフェインが多く含まれる被覆栽培の玉露 など
50〜60度くらいの温度で2分間しっかりと浸出する
・タンニンが多く含まれる煎茶 など
70〜90度くらいの高温で1分間浸出して注ぐ
浸出時間が長ければ味が濃くなるため、好みに合わせて淹れるのが良いでしょう。最近では、水出しのティーバッグなどもありますが、栄養素の溶出を考えるとお湯で淹れるのがベターと言えるでしょう。
緑茶を飲む量
緑茶にはカフェインが含まれるため、摂りすぎることにより動悸やめまい、不眠や不安感などが引き起こされる可能性があります。また、緑茶に含まれるカテキンには胃粘膜を薄くする働きがあるため、胸やけや胃もたれ、胃痛などが生じる可能性があります。さらに、両茶に含まれるシュウ酸という成分は、尿路結石を形成する成分です。どのため、体質的に力尿路結石ができやすい人は摂り過ぎないのが良いでしょう。
研究結果によると、1日4杯以上とることで生活習慣病などの予防効果があるとされていますが、カフェインの許容量や胃腸の強さなどには個人差があるため、自身の体の状態と相談して摂取量を決めるのが良いでしょう。
また、市販でも様々なペットボトルのお茶が販売されています。これらの製品は栄養成分も含まれていますが、日持ちさせるために保存料も含まれています。そのため、緑茶を摂ることで健康効果を得たいのであれば茶葉から淹れるのが良いでしょう。
まとめ
緑茶には様々な栄養成分が含まれており、上手に日常生活に取り入れることにより健康の保持増進の効果を得ることができると言えます。しかし一方で、健康効果を求める余り摂るタイミングや量を間違ってしまうと、健康を害する可能性もあります。生活習慣の中に取り入れる際には、自分に合った量やタイミングにすることを念頭に入れておくことが大切です。
また、健康の基本は、毎日の食事、運動、睡眠です。これらの生活習慣を整えることも忘れないようにしましょう。