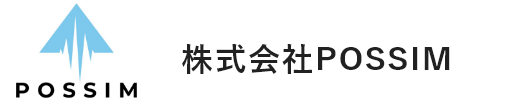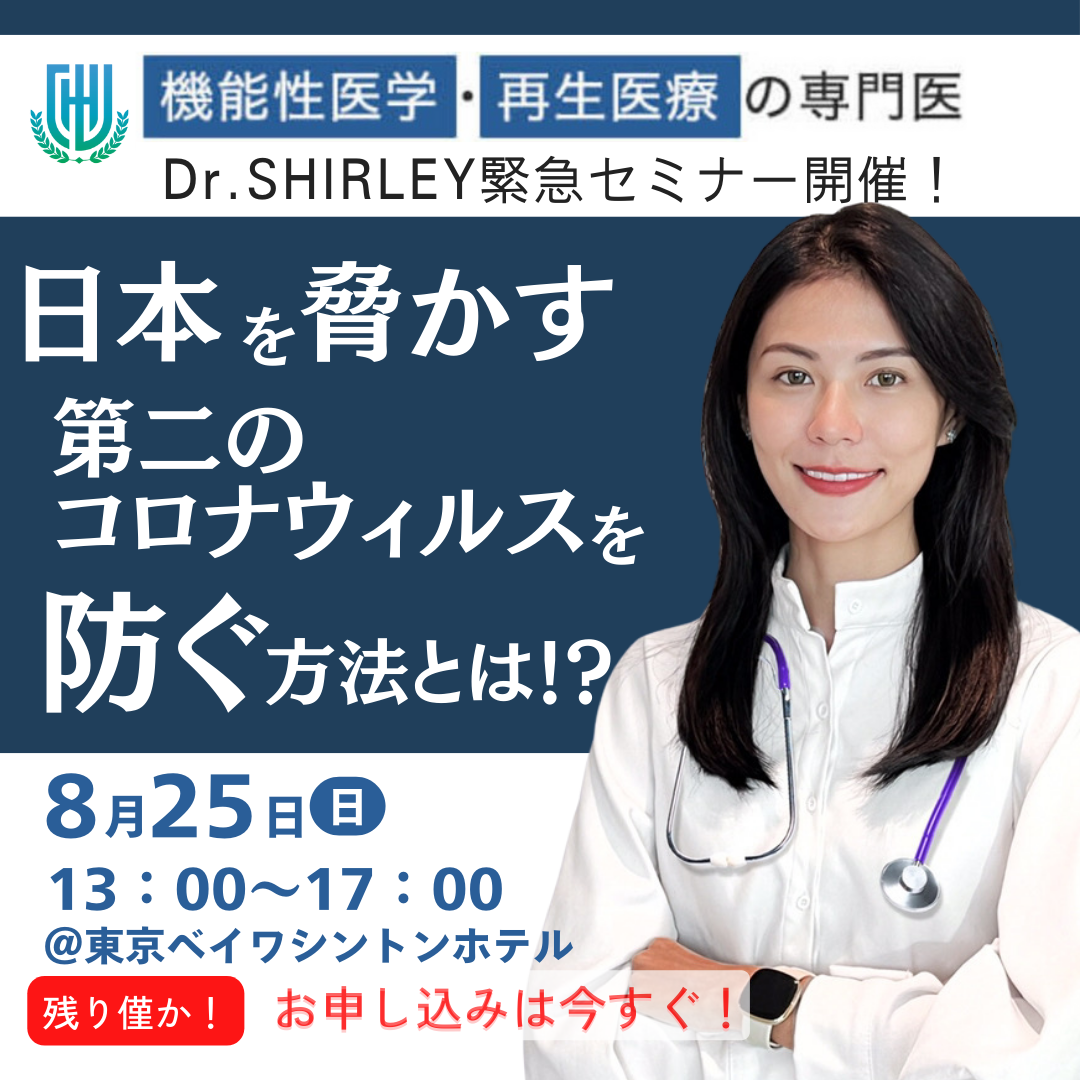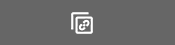冬になると決まって世間を騒がせるニュースの一つに「インフルエンザ」があります。みなさんはインフルエンザについてしっかり理解していますか?
今回は、インフルエンザを予防するための食べ物・予防効果・インフルエンザにかかった時に避けたい食べ物を中心に解説していきます。
インフルエンザとは
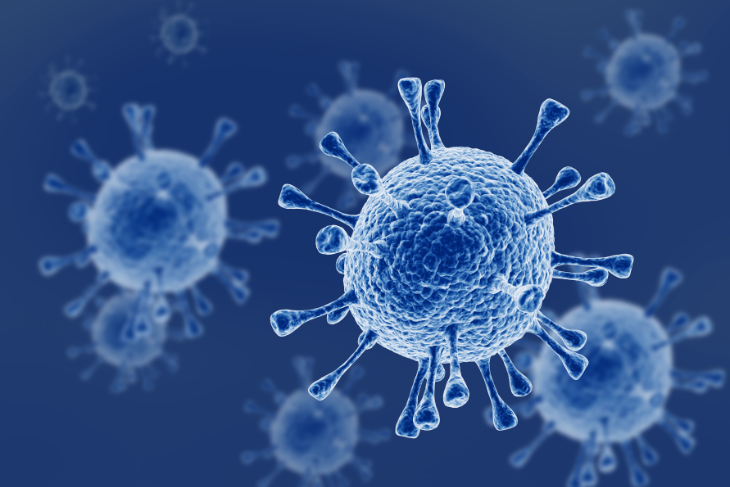
まずはインフルエンザの基本知識から順に解説していきたいと思います。インフルエンザの特徴を知り、ぜひ感染しにくい生活習慣を身に付けてくださいね。
インフルエンザとは?
インフルエンザは「インフルエンザウイルス」を病原とする気道感染症であり、一般的な風邪とは異なり、重症化しやすい疾患です。流行期には特に注意が必要です。インフルエンザウイルスには主にA型とB型があり、A型は例年冬の初めごろ(12月~1月)に流行することが多く、B型はそれに続いて2月以降に流行する傾向があります。
インフルエンザの症状
インフルエンザの潜伏期間は、感染を受けてから1~3日ほどで、その後38℃以上の高熱・頭痛・全身倦怠感・筋肉痛・関節痛などの症状が現れます。またこれらの症状が治まってきたら次に咳・鼻水などの上気道炎症状が現れ、約1週間で症状が軽くなるのが一般的なインフルエンザの症状です。
特に高齢者や呼吸器・循環器・腎臓に疾患を持つ人・糖尿病などの代謝疾患・免疫機能が低下している人がインフルエンザにかかると、症状が悪化して細菌感染症や合併症を引き起こす可能性も高いため注意が必要です。
インフルエンザが冬に流行る理由
インフルエンザウイルスが好む環境は低温で乾燥した空間で、この条件が満たされている場所では比較的長時間にわたって生存し、感染力を保持しやすいとされています。それでは、インフルエンザが冬に流行る要因について項目別にご紹介しましょう。
空気の乾燥
冬は乾燥した空気が広がるため、インフルエンザウイルスが生存しやすい環境が整います。湿度が高い環境では、飛沫中のウイルスが水分を含んで重くなり、地面に落下することで感染の可能性が低下します。一方で、乾燥した空気では飛沫が軽いため、ウイルスが空気中を長時間浮遊しやすくなり、飛沫感染のリスクが高まります。
また、乾燥した空気は人間の気道粘膜を乾燥させ、防御機能を低下させるため、感染のリスクがさらに高くなります。
気温の低さ
冬の低温環境は、以下のようにインフルエンザ感染のリスクを高めます。
ウイルスの安定性が向上:低温環境ではインフルエンザウイルスの膜が安定し、感染力を維持しやすくなります。
粘膜防御の低下:気温が低いと鼻や喉の粘膜が乾燥しやすくなり、外部からのウイルス侵入を防ぐ機能が低下します。その結果、ウイルスが体内に侵入しやすくなります。
日照時間
冬は日照時間が短いため、体内で生成されるビタミンDの量が減少する可能性があります。ビタミンDは免疫機能を調節し、感染症への抵抗力を高める重要な栄養素です。そのため、ビタミンDが不足すると免疫力が低下し、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるとされています。
インフルエンザ予防に効果的な食べ物

ここからはインフルエンザを予防するのに効果的な食べ物について解説していきます。
免疫力を高める食べ物
インフルエンザウイルスを予防するためには免疫力を高める食べ物を摂取することが有効です。では、いったいどんな食べ物を積極的に口にすると良いのでしょう。摂取してほしい各栄養素を含む食品・栄養・予防効果についてご紹介します。
| 食品 | 栄養 | 予防効果 | |
| ビタミンD | イワシ丸干し・カレイ・サンマ・シラス干し・サケ・ブリ・干し椎茸・きくらげ | カルシウム・骨の成長促進/血中カルシウムの濃度を調節する/免役機能を調整する | 免疫機能を調整する働きがあるため、体内に侵入してきたウイルスに抵抗し、必要な免役機能を促す役割を果たしている |
| カテキン | 緑茶・紅茶・ウーロン茶・りんご・ブドウ・チョコレート | 抗酸化作用・抗ウイルス作用・殺菌作用・抗菌作用 | 細菌にもウイルスにも効果があり。体内に入ったウイルスが細胞内で増殖できないようにする報告あり。 |
| ビタミンA | レバー・バター・卵黄・人参・うなぎ・モロヘイヤ・ほうれん草 | 目や皮膚の粘膜を健康に保ち、抵抗力を強める役割がある | 抗感染症ビタミンと評されており、体内に侵入したウイルスに対抗するリンパ球などの白血球細胞の発生や分化に欠かせないもの |
| ビタミンC | パプリカ・キャベツ・ブロッコリー・ミニトマト・サツマイモ・キウイフルーツ・イチゴ・みかん | 皮膚・粘膜の健康維持を促進させ、抗酸化作用を持つ | 免疫力を高める作用を持ち、不足すると免疫力が低下しウイルスにかかりやすくなる。 |
インフルエンザにかかったら?

インフルエンザにかかってしまった場合、どのような点に注意しながら身体を休めると良いのでしょう。
身体をあたためる
インフルエンザにかかった場合、安静にして体力の消耗を防ぐことが重要です。適切な室温(18~22℃)と湿度(40~60%)を保つことで、気道粘膜の乾燥を防ぎ、症状を和らげる助けとなります。湿度が高すぎるとカビやダニの増殖につながるため注意が必要です。また、換気をこまめに行い、室内の空気を清潔に保つことも大切です。
睡眠を十分とる
十分な睡眠は免疫機能をサポートし、体の回復を促します。インフルエンザにかかっている間は、体が感染と戦うため多くのエネルギーを必要とします。日中も無理をせず横になるなど、可能な限り休養を心掛けてください。
栄養のある食事を摂る
インフルエンザにかかってしまったら辛い症状が続いてしまいますよね。そんな時は消化に優しい状態に調理されたもので、口当たりは柔らかく滑らかなものがおすすめです。もし嘔吐・下痢などの症状がある場合は、脱水症状を起こさないために、水分・ミネラルを十分摂取する必要があります。
食欲があるとき
インフルエンザにかかっていても食欲がある場合は、食材を良く煮込んで柔らかくし、消化しやすい食事がベストです。野菜スープ・雑炊・おかゆなど、じっくり煮込んで柔らかくなっている食べ物を、しっかり噛んで食べるようにしてください。おかゆを作る際は、卵を入れたり梅干しを少し入れてもタンパク質・ミネラルが補えるため手軽でおすすめです。
食欲がないとき
食欲がない時は無理に食べようとせず、水分補給だけこまめに行い安静にするようにしてください。食事がとれない場合は、イオン飲料・経口補水液・ゼリー飲料などでミネラル・ビタミンを補うように心がけてください。
インフルエンザにかかっているときは胃腸も弱っているため、冷たいものを飲むのではなくなるべく常温に近い状態のものを口にするようにしてください。
解熱後の回復期
熱も下がり体調もかなり回復してきた時期になると、食欲も戻ってくる人が大半だと思います。とはいえ、数日間食事の量が減っていた胃腸に、一度にたくさんの食事が入ってくると負担が大きくなります。
解熱後の回復期は、それまでと同様に消化が良く胃腸に刺激や負担がかかりにくい食事を心掛けてください。お腹の調子を見ながら少しずつ食事量を増やしていくことで、インフルエンザで崩れてしまった栄養バランスの改善に努めることが大切です。
インフルエンザの時に避けたい食事

インフルエンザにかかっているときに避けたい食事には、どのようなものがあるのでしょう。
消化に悪い食べ物
インフルエンザにかかったとき、インスタント食品・脂っこいものなど、消化に悪い食べ物は避けるようにしてください。これらの食べ物は、消化の際に時間がかかり胃腸に負担をかけてしまうため、ただでもインフルエンザで弱っている胃腸にさらなる負担をかけてしまいます。
甘い物やアルコール
甘い物:甘い菓子やジュースに含まれる砂糖は、過剰摂取すると血糖値を急激に上昇させ、体が回復に必要なエネルギーの効率的利用を妨げる可能性があります。また、胃腸に負担をかける場合があります。
アルコール:アルコールは肝臓で代謝される際に体内のビタミンB群を消費するため、回復の妨げになる可能性があります。また、脱水を促進するため、体の水分バランスを崩しやすくなります。
刺激の強いもの
インフルエンザにかかっているときに、唐辛子系などの刺激の強いものを摂取すると、胃腸をさらに荒れさせてしまうため避ける方が無難です。また刺激が強いものや酸味が強いものは、喉の痛み・咳を酷くしてしまう可能性が高いため控えてください。
食物繊維を多く含む食材
食物繊維を多く含む野菜や豆類は腸内環境を整える効果がありますが、インフルエンザにかかっている時は消化に時間がかかるため、弱った胃腸に負担をかける可能性があります。そのため、過剰摂取は避け、柔らかく調理した野菜や少量の繊維を含む食品(例:じゃがいも、にんじん)を選ぶと良いでしょう。
カフェインを多く含むもの
緑茶・コーヒーなどのカフェインを多く含む飲み物は、水分を体外に排出する働きがあるため、脱水症状を悪化させる可能性があります。インフルエンザ予防にはカフェインは効果的ですが、インフルエンザにかかってしまった時は水・経口補水液・麦茶などのノンカフェインの飲み物を飲むようにしてください。
まとめ
インフルエンザは予防する前とかかってしまった後とでは、食べた方が良いもの・注意すべき点が異なります。そのことについて理解を深め、是非インフルエンザ対策を万全にしてくださいね。